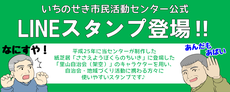毎月さまざまなテーマで地域づくりについて考えていくコラムです。

※お願い※
記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。
無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。
第78話(idea 2025年9月号掲載)
今月のテーマ
地域運営の落とし穴 (62)
学生の「学び」と、地域の「やるべきこと」
過去の本頁(2023年6月号掲載「若者はワカモノらしく」)でも扱ったように、「若者は政策や制度なんて気にしないで、若者らしく過ごして欲しい」と思っているのですが、相変わらず「地域課題の解決に若者(あるいは学生)の参加を」という見出しの記事をよく目にします。
地域課題は、今に始まったことではなく、どちらかというと‘人の多かった時代の仕組み’が現代に合わなくなったり、隙間が生じてしまったのが要因。若者や学生は、そもそもの背景を知らなかったり未経験だったりするため、時には彼らの意見を聞きつつも大人世代がしっかりと議論するべきで、わざわざ巻き込む必要はないのです。
学生は、本来すべきことがあり、学生時代だからこその時間を大切に過ごしてほしいため、私自身は学生の関わりをあまり意識していません。もちろん、好きで関わる学生もいますが、高等学校の「探究の時間」などが後押しし、地域の課題解決に学生が参加する構図が出来上がってきているのが現状です。しかし、ここで注意すべきことがあります。
そもそも「探究(総合的な学習)の時間」とは、『変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしている(文部科学省HPより引用)』ものです(小・中学校=「総合的な学習の時間」、高等学校=「総合的な探究の時間」)。導入された背景には、これまでの‘受け身の学習’から、自分事として疑問や課題を自ら解決しようとする力を磨いていく‘主体的な学び’へと転換する目的がありました。知識や情報を頭に入れる(インプット)だけでは応用が利かず、社会に出た時の対応能力の低下につながるため、自ら考える力を養い、柔軟な対応ができる人材育成の必要性から始まったのではと推測しています。
つまり、「探究の時間」は、「なぜ?なぜ?」と考えていく論理的思考(ロジカルシンキング)を養うために導入されたのであって、課題解決の成果(アウトプット)を求めるものではないのですが、なぜか成果を求める風潮が強く……。大人側が「あのプロジェクトは、こんな素晴らしいことをやった」「学生らしい素敵な取り組みだ」など評価してしまっています。成果を評価するのではなく、学生が、何をきっかけに、どんな考え方をして、どのような対策を考えたのか、そのプロセスを評価してあげるべきなのです。地域づくりに学生を関わらせた際も同様の場面が散見されますが、成果が欲しいのであれば、大人が責任を持ってしっかり考え、予算をつけ、変わる勇気を持って取り組むべきです。
そもそも、‘学生が感じる課題’と‘地域が感じる課題’はイコールではありません。学生に対し「地域の課題はこんなことがある」と、学ばせる(インプット)時点で、「この課題に対して何か考えて」とオーダーしているようなものです。‘誰かが考えた課題を考える’のと‘自ら課題と感じたことを考える’のでは、熱の入り方も違います。
地域づくり事例として学生と地域が一緒に取り組んだものが挙げられたりしますが、その裏側では、複雑な課題が生まれていることもしばしば。
大学生のフィールドワーク(調査対象となる現場に直接訪れて情報収集する研究方法)では、地域が大学生を受け入れて半年ほど一緒に活動することがあるのですが、数回続けていくうちに、地域側から「去年の学生は良かったが、今年の学生は……」と、学生の質を問うようになってしまうことがありました。学生を作業要員として扱ったことにより、地域住民が地域づくりに積極的に関わらなくなっていき、学生の受け入れが無くなった途端に地域だけで担いきれなくなってしまったのです。学生を当てにしすぎて、地域側の力が弱くなってしまった事例と言えます。逆のパターンもあり、一生懸命関わる学生たちの熱が入りすぎてしまい、自分たちのやりたいことだけが中心で、地域の意思決定とは異なり、住民を困らせる事例もありました。
これらの事例はよくある話で、目的の喪失から生じることです。地域側は実践する側で、学生は実践ではなく学びが優先であるため、目的をはき違えないようにしましょう。
- idea 2025
- 過去の情報紙idea(PDFデータ)
- 団体紹介
- 地域紹介
- 企業紹介
- 博識杜のフクロウ博士
- 第77話 地域づくりは生きる対策
- 第76話 地域と行政のつながり
- 第75話 地域の役割や各種団体の目的の再確認を!
- 第74話 地域協働体について(再確認用)
- 第73話 働く幸せ
- 第72話 事例の取り扱いにご用心
- 第71話 地域コミュニティは、消滅する?
- 第70話 お手当のはなし
- 第69話 昔の良さって何を指す?
- 第68話 「多様性」「個人情報」意味を正しく理解する
- 第67話 ボランティアで関わることは損なのか?
- 第66話 地域協働体(RMO)の 存在意義
- 第65話 子どもの教育環境は 連携・協働で!
- 第64話 子どもの仕事
- 第63話 「変わり目」にご用心
- 第62話 地域協働体はRMOなの?
- 第61話 看板を背負うのは時代遅れなのか?
- 第60話 失うものの代償
- 第59話 ボランティアは「小間使い」ではない
- 第58話 実績を残したいのか、名を残したいのか
- 第57話 交流事業にみる人材育成
- 第56話 スマート農業
- 第55話 ‘多様性’の難しさ
- 第54話 「安心安全」 を脅かす 「目に見えない危険」
- 第53話 改めて、新型コロナ5類移行後の地域づくり
- 第52話 規格外にも、プライドがある
- 第51話 若者はワカモノらしく
- 第50話 農村RMOと地域協働体
- 第49話 農村RMOと農業施策
- 第48話 「農村RMO」の出現
- 第47話 「コミュニティ支援」のスキルとは?
- 第46話 まやかしの‘課題解決’
- 第45話 「中間支援」は、必要なのか?
- 第44話 NPO=コミュニティビジネス
- 第43話 がんばれNPO
- 第42話 地域運営における各種団体の底力を侮るな
- 第41話 見直しは勧めるが、見直しのし過ぎはご用心
- 第40話 地域は、活性化を求めているか?
- 第39話 情報発信は「予告」よりも「共有」重視!?
- 第38話 担当者の個性が見える!? 「自治会広報」
- 第37話 「役の交代」についての傾向と対策
- 第36話 「『地域文化』の継承」は、誰が、どうやって?
- 第35話 「急がば回れ」 の ‘人材育成’
- 第34話 空き缶を拾うのは市民の権利である
- 第33話 「文化活動」は後回しにしてはいけない
- 第32話 見えない価値こそ高値である
- 第31話 「耳障りの良い」言葉
- 第30話 ワークショップの落とし穴②
- 第29話 ワークショップの落とし穴①
- 第28話 新しい(?)家庭教育
- 第27話 「職業コーディネーター」の存在
- 第26話 「地域の特色」とは?
- 第25話 地域づくりに「オンライン」はマッチするか?
- 第24話 コロナ禍における地域運営
- 第23話 若者は本当に地域のことに興味がないのか?
- 第22話 世代間の意識の違い~‘働き方’=‘暮らし方’~
- 第21話 中高年こそ理解すべきSNSマナー
- 第20話 知られざる「著作隣接権」
- 第19話 ‘純粋な’自治会費はおいくら???
- 第18話 「負担金ルール」に見る時代の変化
- 第17話 「自治会」への加入は義務???
- 第16話 協議体と協働体
- 第15話 地域での支えあい(生活支援体制整備事業)
- 第14話 制度が壊す地域の絆
- 第13話 地域づくりと地域福祉
- 第12話 地域づくりと市民センター
- 第11話 地域づくりと社会教育
- 第10話 地域協働体の動き方
- 第9話 円卓会議の意義
- 第8話 地域協働体とは?
- 第7話 協働の領域
- 第6話 なぜ一関市は地域協働を語り始めたのか?
- 第5話 地域協働とは
- 第4話 地域づくりの視点
- 第3話 地域づくりがおすすめ?
- 第2話 いま、なぜ まちづくりなのか?
- 第1話 地域づくりガイダンス
- センターの自由研究
- 二言三言
開館時間
9時~18時
休館日
祝祭日
年末年始
(12月29日から翌年1月3日まで)
いちのせき市民活動センター
〒021-0881
岩手県一関市大町4-29
なのはなプラザ4F
TEL:0191-26-6400
FAX:0191-26-6415
Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp
せんまやサテライト
〒029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字町149
TEL:0191-48-3735
FAX:0191-48-3736
X(旧:Twitter)公式アカウント
Facebook公式アカウント
LINE公式アカウント
駐車場のご案内
なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。
当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。
1. なのはなプラザ駐車場(無料)
2. 一関市立一関図書館(無料)
3. 地主町駐車場
4. 一ノ関駅西口南駐車場
5. 一ノ関駅西口北駐車場
6. なの花AB駐車場
7. 大町なかパーキング
8. マルシメ駐車場