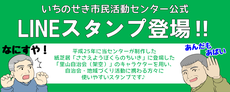※お願い※
記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。
無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。
伝説調査 ファイルNo.10 「矢越山」
(idea2025年8月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。
室根町で3番目に高い山「矢越山」。標高519.6mながら、北に室根山、北西に束稲山、南に太田山、大森山、東には気仙沼市街と気仙沼湾、その遠方に太平洋が見えるなど、360度のパノラマが楽しめます。また、ヤマツツジの開花時期には、山が真っ赤に染まるなど、魅力あふれる山です。そんな「矢越山」には、山名の由来となったとある伝説が……。伝説をご紹介するとともに、ゆかりのあるスポットを巡ってみました。
※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。
900年以上前の伝説
「矢越山」は「森は海の恋人植樹祭」の植樹会場として、その存在自体は広く知られています。明治22年には上折壁村と釘子村が合併し、山名を由来とした「矢越村」も誕生しています(昭和30年に室根村へ)。
ところで、この「矢越山」の名称には、ある伝説が存在します。
・源義家が蝦夷征伐でこの地に来た時、戦勝を祈願し、釘子から羽山(釘山)に向かって矢を放った。
・義家の射た矢は羽山(釘山)を越え、浜横沢に落ちた。
・矢が超えた山(羽山/釘山)をそれ以降は「矢越山」、浜横沢の矢が留まったところを「留」と呼び、留には「矢留大明神」が祀られた。
様々な文献資料に、若干のニュアンスは違えど、上記のような趣旨の伝説が記載されています。「弓矢が山を越えた」という、現実的には起こり得ないような事象が由来になっているのです。
源義家の蝦夷征伐と言うのは、1051年に勃発した前九年の役を指します。この時の陸奥守は義家の父・源頼義でしたが、「黄海の戦い(1057年)」で蝦夷・安倍軍に大敗し、頼義も窮地に陥ります。その窮地を救ったのが、息子の義家でした。義家は当時まだ18歳でしたが、自他ともに認める弓矢の名手で、その後は「小松柵の戦い(現在の一関市萩荘上黒沢)」・「衣川関の戦い」に勝利し、「厨川の戦い」で安倍氏を滅亡させます(1062年)。
前九年の役における活躍で、義家は武士としての名声を高め、岩手県内をはじめ、東北や京都に至るまで、各地に伝説(ゆかりの地)を残しており、弓矢に関する伝説も多くあります。
ここで疑問が。なぜ前九年の役の戦地ではない室根に、義家伝説(八幡太郎義家)があるのでしょうか。
どこまでが史実か?
その答えは室根神社にあります。室根神社は、718年、時の鎮守府将軍大野東人が、蝦夷征伐に神の加護を頼ろうと、熊野大社(現在の和歌山県田辺市)の御心霊を勧請したもので、室根山に鎮座しています。810年には坂上田村麻呂も訪れ、蝦夷征伐の祈願所となっていました。
頼義・義家父子も同様に、安倍氏滅亡に神の加護を頼るべく、室根神社を参拝したとされるのです。『室根神社史実録』によると、1052年には頼義が、その後は義家も連れ、父子で参拝しているという記録が。室根への来訪は史実としてあり得そうです。
室根を来訪した際、上記伝説のように矢を放ったとしても、釘子から浜横沢までの距離は直線距離でも5.1㎞。弓矢の名手・義家とて、さすがに無理があります。
とは言え、900年以上も前の伝説が、口伝ベースで語り継がれてきたこと自体がすごいこと。しかも、この伝説、深堀りをしていくと、興味深い事実が見えてくるのです……!
| 1051 | 「鬼切部の戦い」で前九年の役勃発 |
| 1052 |
頼義が室根神社に参拝し、祈願文を奉納 「今度蝦夷頼時父子誅滅祈願のため神馬一、 太刀一寄進せしむる者なり |
| 1057 |
?月 頼義・義家父子、室根神社に参拝し桜を植樹 |
|
11月 「黄海の戦い」 →頼義の窮地を嫡男の源義家(当時18歳)が救う |
|
| 1062 |
9月 厨川柵が陥落 |
|
安倍氏の乱を平定した義家が室根神社に参拝し、 社寺に造営を加え、社領三万刈を寄進 |
|
| 1066 | 義家が矢留大明神を勧請、矢越神社殿を建立 |
源義家の矢越山伝説を深堀りしてみた
ここまでご紹介した通り、源義家が「釘子から羽山(矢越山)に向かって矢を放った」ことにより、様々な「義家ゆかりスポット」が生まれています。その「義家ゆかりスポット」をご紹介するとともに、「義家が弓矢を放った場所はどこなのか」を深堀りしてみます。
矢留大明神

伝説の通り、浜横沢には「留」という小字が存在し、留に居住する千葉家の敷地内に「矢留大明神」と呼ばれる祠があります。
現在の当主・千葉孝さんは、祖父母から「八幡太郎義家の打った矢が落ちた」という話を聞かされたそうですが、それ以上の詳細は分からないとのこと。祠は20年以上前に屋根を直したほか、何度か手を加えられていると思われますが、「骨組みは昔のまま」と聞いているそう。
なお、孝さん宅の屋号は「留の上」で、「留の下」という屋号の家が近くにあるとか(分家)。弓矢の名手・義家にあやかってか、戦時中には出征した兵士の家族などがお参りに来ていたという話も。

◀千葉家の屋敷奥の小高い場所に祠がある。祭神を「正一位矢止稲荷大明神」と記載した文献もあるが、実際には不明。神棚の上方に「柱に布を巻いた御神体」があるそうだが、その詳細も不明。現在は御幣束を5本捧げている。
矢越神社

治歴2年(1066年)に義家が勧請したとする説もありますが、文献によって曖昧です。祭神は武甕槌神とされますが、義家の放った征矢を祀ったとする文献も(前者の場合、義家が勇猛の神である武甕槌神に陣中で祈願したことが由縁)。
矢越山伝説を調べている矢越在住の渡邊精一さんによると、安永4年(1775年)の『風土記御用書出』には「風土記を書くにあたって矢越神社内を探したが、義家の矢はなかった」という趣旨の記述があるとのこと。つまり遅くとも江戸中期には史実不明状態での口伝になっていたのです。
射勢山愛宕神社
彌榮(弥栄)神社

勧請年は不明ですが、安倍氏の乱平定後に祠が建てられ、祇園素戔嗚命を祀ったとされます(義家の父・頼義が東夷征伐の前に現在の八坂神社(京都府・祇園)に逆賊平定を祈ったとされ、その関係)。
義家がこの境内地から釘山に矢を放ったことから「遠矢森」という地名になったとされます(現在は「鳥矢森(とやもり)」)。
足尾山碑(矢越山伝説発祥の地/義家の足型)

この石碑の台座になっている石には、人の足型のような窪みが!この窪みは義家が征矢を射った際についた足型として伝承されており、「矢越山伝説発祥の地」という看板が(残念ながら風化で現在は文字が見えない)。なお、この足型のついた石は、道路整備の際に数百メートル移動された経過が。元々あった場所を地元の人に教えてもらったところ、驚きの発見が……!
義家はどこから矢を放った⁉
伝説では「釘子から射た」とされていますが、上で紹介した通り、その候補地は2か所あります(実際にはもう1か所あるようですが、詳細つかめず)。
そのうち「矢越山伝説発祥の地」という伝承の残る、足型の石が本来あったとされる場所と、矢が落ちた先の「矢留大明神」を線で結ぶと、なんと、その直線上に「矢越神社」が重なるという奇跡が!

実は矢越山伝説を調べている渡邊精一さんも同じく直線で結ばれることを発見しており、意気投合(笑)
歴史ロマンの世界ではありますが、義家が矢を放った場所は室根町矢越の馬場(足型の石があった小字)だったと仮定させていただきます!(もちろん所説あり)
【誌面こぼれ話】
誌面でも少し登場していますが、矢越在住の渡邊精一さんが『矢越地名伝説』という本をまとめています(自家製本/非売品)。この本の存在を知らず、矢越山伝説を自力で調べていた我々、地元の方にヒアリングをする中で「渡邊精一さんがすでに詳しく調べているよ」と教えられ、会いにいったのですが、こちらが調べる余地のないほど詳しく調査研究されていて、びっくりしました(笑)
源義家は、室根町の矢越山伝説だけでなく、全国各地に伝説を残しており、ゆかりの地は様々あります。当市内にも実はたくさんあります。
そして福島県白河市には「矢越」という地名で、かつ、伝説の中身も室根町の「矢越」とそっくりな義家伝説があるのです。※もちろん渡邊精一さんの本でも紹介されています(笑)
実は今回、誌面では触れられませんでしたが、室根における「矢越山伝説」の中には下記のようなくだりがあります。
「釘子から義家によって放たれた矢が、矢越山を越え、浜横沢の空を飛ぶとき、風を切る音がスワスワと音を立てて飛んだと言われ、今の浜横沢小学校の近くに「スワ八幡様」を祀ったといい伝えられています。」
今回の調査の中で、「スワ八幡様」も探したのですが、地元の人に聞いても分からず(唯一の情報は「昔、ばあちゃんたちが‘オスワさん’と言っていたのを聞いた気がする」という話)、今も現存するのかどうかすら定かではありません。
ただ、江戸時代(元禄11年のものを文政6年に追記縮小)の絵地図の中では「スハ八マン」という表記を発見!場所も旧浜横沢小学校の辺りだったため、これが「スワ八幡様」なのではないかと思われます。推測ですが、浜横沢小学校の校舎建築の際に、取り壊されたり、どこかに合祀されたのかもしれません。
ちなみに、先ほどご紹介した福島県白河市にも「諏訪神社」があるようです。関連性は不明ですが、歴史の奥深さ、面白さを感じずにはいられませんね。
▲明治40年頃の浜横沢小学校の写真では、校舎の周囲が林になっており、この林の中に「スワ八幡様」があった可能性が。昭和52年の写真だと、林がなくなり、校庭が造成されており(校舎も移転)、この時になくなったのではないかと推測します。
※写真は旧浜横沢小学校の校長室に飾ってあったものを、地域の人が撮影したもの(を、提供いただきました)。
<参考文献> ※順不同
・渡邊精一(2023)『矢越地名伝説』
・室根村史編纂委員会(2004)『室根村史 上巻』
・室根村文化財調査委員会(1995)『室根村の神社とお寺』
・室根村文化財調査委員会(1997)『室根の字地名』
・澤本健三(1934)『日本国勢総覧 上巻』
・福島県西白河郡役所(1915)『西白河郡誌』
・編/同 記念誌編集委員会委員長 畠山喜一(2000)『発信-東磐井のあしあと』
発/東磐史学会創立五十周年記念事業 実行委員長、東磐史学会会長 小野寺一郎
・小山伊造(1885)『室根神社由来明細記』
・室根村教育委員会教育長吉田幸八(1969)『室根神社史実録』
・黄海村史編纂委員会(1960)『黄海村史』
↓実際の誌面ではこのように掲載されております。
- idea 2025
- 過去の情報紙idea(PDFデータ)
- 団体紹介
- 地域紹介
- 企業紹介
- 博識杜のフクロウ博士
- センターの自由研究
- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.10 「矢越山」
- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.6「冨永シゲヨ」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.30 「橋②」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.30 「橋①」
- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.9 ヘビ
- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌大原
- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.6「馬喰」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.29「畑作の変遷」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.28「メダカ」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.27「俚謡(餅つき唄)」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.26「ママさんパパさんバレー②」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.26「ママさんパパさんバレー①」
- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え」(密着こぼれ話)
- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え②」
- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え①」
- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.5「千葉胤秀」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.25「照井堰用水」
- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.10「関」と「堰」
- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌磐清水
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.24「(家庭における)民間療法」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.23「火のある暮らし」
- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.9「二関村②」
- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.9「二関①」
- センターの自由研究 いにしえの道ファイルNo.1「花泉~気仙沼②」
- センターの自由研究 いにしえの道ファイルNo.1「花泉~気仙沼①」
- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.8 「興田と沖田」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.22 「調理の習わし」
- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.7「ウサギ」がつく地名
- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.4 「千葉土佐」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.21「年(歳)神様の迎え方②」
- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.21「年(歳)神様の迎え方①」
- センターの自由研究 仕事の流儀 ファイルNo.4「炭焼き②」
- センターの自由研究 仕事の流儀 ファイルNo.4「炭焼き①」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.20「講」「頼母子」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.19「こうせん粉」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.18「たばこどき」
- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.6 「黄海(きのみ)」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.17 「来客に出す飲み物」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.16 「冷蔵庫のないくらし②」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.16 「冷蔵庫のないくらし①」
- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.8 「かさこ地蔵」
- センターの自由研究 末裔調査 ファイルNo.3 昆野八郎右衛門
- 【本誌こぼれ記事】昆野八郎右衛門
- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.7 金山一揆(後編)
- 【本誌こぼれ記事】金山・鉱山マップ
- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.7 金山一揆(前編)
- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌東山
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.15 「孫抱き」
- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.5 「奥玉」※「摺沢」続編
- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.4 「摺沢の水晶」
- センターの自由研究 末裔調査 ファイルNo.2 「宮城山福松」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.14「舟のある暮らし」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.13「嫁取り」
- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.12「間取り」
- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.3「狐禅寺」
- センターの自由研究 仕事の流儀No.2「葉たばこ」~後編②~
- センターの自由研究 仕事の流儀No.2「葉たばこ」~後編①~
- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌藤沢
- センターの自由研究 仕事の流儀No.3「たたら製鉄」
- センターの自由研究 境目調査ファイルNo.2「イノシシ」
- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.1「芦東山」
- センターの自由研究 境目調査ファイルNo.1「旧藤沢町」
- センターの自由研究 伝説調査ファイル№6「鬼死骸(村)伝説」
- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌永井
- センターの自由研究 仕事の流儀№2「葉たばこ」前編
- 【本誌こぼれ記事】オシラサマのキニナルあれこれ
- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.6「オシラサマ」
- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.5「オカミサマ」
- 【本誌こぼれ記事】門かぶり松ギャラリー①
- 【本誌こぼれ記事】門かぶり松ギャラリー②
- センターの自由研究 門かぶり松
- センターの自由研究 伝説調査ファイル№4 舞草鍛冶
- センターの自由研究 「巨樹」探訪vol.4 割山のケヤキ
- センターの自由研究 難解・難読地名調査in室根
- センターの自由研究 仕事の流儀№1「養蚕」後編
- センターの自由研究 仕事の流儀№1「養蚕」前編
- センターの自由研究 伝説調査ファイル№3「河童伝説」
- センターの自由研究 巨石調査ファイル№4「立石」
- センターの自由研究 市内で1番段数が多い石段はどこだ!?
- センターの自由研究 「巨樹」探訪 vol.3
- センターの自由研究 「巨樹」探訪 vol.2
- センターの自由研究 「巨樹」探訪 vol.1
- センターの自由研究 難解地名に挑戦!in 萩荘
- センターの自由研究 市内の気になる巨石~大猊鼻岩~
- センターの自由研究 「おためし神事」
- センターの自由研究 市内の気になる巨石~立石神社~
- センターの自由研究 市内で一番大きな巨石は!?
- センターの自由研究 運動会のおもしろ種目
- 100人?に聞きました!難解地名に挑戦!
- センターの自由研究 鳩レースの世界
- センターの自由研究 地蔵田
- センターの独自調査 ごみステーション
- 100人?に聞きました!難解地名に挑戦!
- センターの自由研究 ”かま神様”
- センターの自由研究 厄年行事(年祝い)
- センターの自由研究 大根の年越し
- センターの自由研究 一関の餅のルーツ
- センターの自由研究 おらほの〇〇坂
- センターの自由研究「盆棚」
- センターの自由研究 一関市の長屋門②
- センターの自由研究 一関市の長屋門①
- センターの自由研究 旧町村・ご当地柄マンホール
- 100人?に聞きました!カドグチ・ジョノグチの違いはあるの?
- センターの自由研究 屋根の調査
- 100人?に聞きました!方言編②
- センター独自調査!方言編 こぼれ話
- センター独自調査!方言編
- センター独自調査!お雑煮編
- センター独自調査!悪魔祓い編
- センター独自調査!イルミネーション編
- センター独自調査!おまんじゅう編
- あぁ~実りの秋だな~稲刈り特集
- 行ってみっぺす!市内のミュージアム
- 夏本番!!夏祭り特集
- 一関の涼を求めて
- こどすも田植えはじまったよ~
- 花よりおらほの‘団子’!
- 気になるあのデータ
- 平成28年度 いちのせき市民活動センター実施事業
- ハプニング大賞2015
- みちのくワークショップフォーラム2015
- 地域イベントを楽しむ秋
- 月初会議ではこんなことを話し合っています
- いちのせき市民フェスタ2015
- インアーチ参観日 参加レポート
- 千厩・藤沢地域担当 佐藤支援員のお仕事術
- まちづくりコーディネーター養成講座
- 地域担当者おすすめ!特選スイーツ!第2弾
- 新年度スタート!10年の歩み
- いちのせき市民活動センター意見交換会
- 地域担当者が発見!特選スイーツ!!
- 狩野支援員のお仕事術
- 2015年もよろしくお願いします
- 地域づくりハンドブックマスター講座の裏側
- 志民のための成長戦略「Hana金!」の裏側
- いちのせき市民フェスタ14の裏側を取材
- わたしたちの一関の未来づくりワークショップ
- 情報誌ideaが出来るまで
- 畠山信禎主任のお仕事レポート
- 佐々木牧恵主任の1日に密着
- 二言三言
開館時間
9時~18時
休館日
祝祭日
年末年始
(12月29日から翌年1月3日まで)
いちのせき市民活動センター
〒021-0881
岩手県一関市大町4-29
なのはなプラザ4F
TEL:0191-26-6400
FAX:0191-26-6415
Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp
せんまやサテライト
〒029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字町149
TEL:0191-48-3735
FAX:0191-48-3736
X(旧:Twitter)公式アカウント
Facebook公式アカウント
LINE公式アカウント
駐車場のご案内
なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。
当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。
1. なのはなプラザ駐車場(無料)
2. 一関市立一関図書館(無料)
3. 地主町駐車場
4. 一ノ関駅西口南駐車場
5. 一ノ関駅西口北駐車場
6. なの花AB駐車場
7. 大町なかパーキング
8. マルシメ駐車場